シチューは西欧食文化の原点(2)
中世末には「フランス料理」の歴史がはじまる

中世の末、フランス料理の歴史に、最初の「グランシェフ」として名を残したタイユヴァン(本名ギョーム・ティレル:1310〜1395)の時代には
- あぶり焼き
- ゆでる
- 揚げる
- 蒸し煮にする、または煮込む
という4種の調理法がありました。彼のレシピにももちろん煮込みは登場しますが、例えばCive de Veel(子牛のシチュー)ではつなぎは小麦粉ではなくぶどう酒に浸したパンを使用しています。
フランス古典料理の基を築き、『フランスの料理人』の著者として知られるラ・ヴァレンヌ(1615頃〜1678)は、煮汁を煮詰めて風味を濃縮することの大切さを知っていました。ブーケガルニ、ケイパー、小麦粉を用いたLapereaux en ragout(兎のラグー)のレシピもあります。
素材も味も変化に富んだシチューは、ロイヤルレシピにもしばしば登場
最後に英国王家の食卓に登場した誇り高いシチューをご紹介しましょう。ミシェル・ブラウン著『ロイヤル・レシピ』によれば、赤毛王ウイリアム2世(1087〜1100)の食卓には鹿肉、かぶ、にんじん、玉ねぎのシチュー、ジョン王(1199〜1216)の場合はうなぎと玉ねぎを使ったサフラン風味のシチューがのりました。そしてエドワード3世(1327〜1377)は前述のタイユヴァンが活躍した時代ですが、マクロー(マカロニ)を添えるスパイスの効いたビーフ・シチュー(とろみは黒パンでつけます)を、リチャード2世(1377〜1399)は料理人2000人を抱えたといわれるグルメでしたが、ハーブやにんにくを詰めたハトのシチュー(おいしそう!)を、フランス人シェフ・カレームを招聘したジョージ4世(1820〜1830)の食卓には、マディーラ・ワインとエスパニョールソースを使ったうずらのシチューが登場しています。
シチューはいつでもどこでも誰にでも作れる便利な料理
ここで「シチュー」という料理をあらためてながめてみると、まず少量の油脂、玉ねぎ・にんじんなどの香味野菜、具材となる家畜の肉やジビエ(野生の鳥獣肉)、ときには臓物類、煮込み可能な他の野菜、とろみをつけて仕上げをよくする澱粉類(古くはパン、後には小麦粉、他に米など)、スパイスや風味付けに役立つさまざまな食材(ワインやビール、乳製品、果実、ココナッツミルクやピーナッツバター、チョコレートなど)と塩、そしてたっぷりの水があれば、あとは深鍋と弱火がきく熱源、それに時間があればよいのです。
肉食文化では家畜を1頭殺せば、一度に食べきれない肉は塩漬にしたり燻製にしたりして保存しますが、塩辛くて味のきついものや、硬くてそのままでは食べられない保存食材も、煮込み料理ならあらたな味を引き出し、全体をおいしくすることができます。
また食べるときも、分けへだてなく同じ鍋から盛り分ければ、切り身の数を争うこともありません。労働に明け暮れる農民や、簡単な調理道具とともに移動することの多い軍隊・牧畜民、誰にでもどこででもわずかな工夫で作れる料理です。
肉食文化の西欧では「シチュー」が食文化の原点であり、その食に欠かせないものになったということはごく自然の成り行きといえましょう。
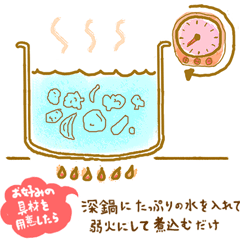
ジビエ(野生の鳥獣肉)とは

フランス語でジビエ(gibier)、英語でゲイム(game)は、牛や豚などの家畜でなく野山で狩りをして手に入れる野生の鳥獣類のこと(現在は飼育しているものもありますが)。
西欧ではこれらジビエ類がとても珍重され、「ごちそう」として供されることも少なくありません。日本にも昔からこうした野生の鳥獣類はありましたが、西欧とはその位置づけが違っているようです。
野生の鳥獣の季節(Game Seasons)
| 英名 | 日本名 | 季節 |
|---|---|---|
| duck | かも | 1年中 |
| wild duck | 野がも | 8月〜1月 |
| teal | こがも | 9月〜3月 |
| wigeon | ひどおりがも | 8月〜3月 |
| goose | がちょう | 9月〜3月 |
| gosling | がちょうの子 | 3月〜9月 |
| grouse | らいちょう | 8月〜12月 |
| blackcock | 黒らいちょう | 10月〜12月 |
| guinea fowl | ほろほろちょう | 10月〜2月 |
| rabbit | うさぎ | 1年中 |
| hare | 野うさぎ | 8月〜2月 |
| quail | うずら | 1月〜8月 |
| partridge | やまうずら | 9月〜2月 |
| pheasant | こうらいきじ | 10月〜2月 |
| pigeon | はと | 8月〜4月 |
| snipe | しぎ | 8月〜3月 |
| woodcock | やましぎ | 8月〜3月 |
| wild boar | 野生のいのしし | 1年中 |